前回、娘の「吃音」についてお話しました。
前回のお話はこちら↓↓

そもそも吃音とは、言葉がスラスラと出てこない言語発達です。
回数を分けながら、吃音との向き合い方や、親としてどういうマインド(心構え)を持ち、
接していくべきか などを発信しています。
吃音の度合いや本人がどこまで気にしているかなどでケースが違ってくると思いますので、あくまでも我が家の場合での情報発信になります。ご了承ください。
前回は吃音のはじまりについてお話しましたが、今回はその後の経過から言語相談を受けようと思うまでについてです。
本記事は、子供の吃音で悩んでいる方、回りで吃音の方と接している方が、
吃音に悩む子が少しでも気持ちよく、楽しく、おしゃべりして
過ごせるための参考になったらうれしいです。
吃音の日々(繰り返し)
「は、は、は、はんぺん」の吃音が初めて出て以来、栓が抜けたように、怒涛に一気に吃音が出始めました。特に繰り返しが多く、話し始めの最初の1文字目を繰り返すという日々になりました。

こ、こ、こ、こ、これはね

わ、わ、わ、わ、わたし

お、お、お、お、おかあさん
聞き手のこちらも「どうして急に、、、、」と戸惑いの日々でした。
急に始まったので、娘も何がなんだか分からない状態で繰り返しの吃音がでていて、話がなかなか進まずに疲れてしまう姿もありました。
緊張して疲れが溜まっていたのかも、、、とのんびり過ごしたり意識して過ごしてみましたが、1週間経っても、2週間経っても、症状は変わらず、、、。
心配になって気になって調べてみると、“吃音”という文字を目にしました。でもその当時はまさか娘がね、、、と思ってスルーしてしまいました。
その時の私は、心配よりも“話し方なんだかもどかしいな…今までスラスラと会話していたのに”と急に会話のテンポも変わり、なかなか話が進まないことに少しイライラしてしまうことさえありました。そんなに重要なこととは捉えていませんでしたし、受け入れることなんて全く出来ていませんでした。

大人でも緊張すると
「こ、こ、これは」、「えっと、えっと、」とか
言ったりするし、娘もそんな感じなのかな!?
これは一過性のもの、いつかおさまるだろう、、、
そう軽く考えて思い込んでいました。
吃音治った??
案の定、1ヶ月くらい続いた時、吃音がパタっとなくなりました。
毎日の会話がスムーズに話せるようになったこと、そして娘もスラスラと話せるようになっって会話が以前のようにできるようになった喜びの表情を見て安堵したのを覚えています。

これで良くなった?これで終わったんだ…
これでもう出ないで欲しい、、、
もう出ないでほしいと思い込んで現実逃避していました。これで終わったと安堵していました。この時は吃音のことがよく分かっていなかったので、吃音に波があることを知らなかったんです。
吃音の波は出る時は怒涛のように出て、パタっと出ない時は2、3ヶ月くらい出ない時もあります。この波にかなり一喜一憂します。夫も一喜一憂していました。
そして私ももちろん一喜一憂していました。
吃音ひどくなった?(引き延ばし)
それから2ヶ月くらい経過すると、また繰り返しの吃音が出始めました。しかも、以前よりも繰り返しの量が増えていました。

わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ
わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ、わ
わたし
最初の「わ」を20回くらい繰り返していました。多い時はと30回くらい繰り返すことも…。再度、吃音が出てことで、私は最初に調べていた「吃音」という言葉が当てはまるのかも知れないと感じていました。でも、その時は対処すればなんとかなる、そぐに治ると思い込んでいました。
娘は吃音なのか?でも違うかも?と自分に自問自答しながらの日々でした。
戸惑いながらも、やらない方がいいとされる「ゆっくり話して」「落ち着いて話して」という声かけはしないように気をつけていました。
そして“どうして…”“なんでまた…”と焦りの気持ちがあったと同時に、またあの会話生活が始まるかと落ち込んでいました。
今では一喜一憂せずに冷静に身守ることが大事ということも分かりますが、当時は分からないことばかりでしたので、とても困惑していたのを覚えています。
そしてネット詮索しては“親の育て方が悪いのではないか”“母親の声のかけ方に問題があるのではないか”と内心自分を責めてばかりいました。
また、小学校に上がる前に吃音のある女子の70%は自然に消滅するという言葉に期待を持っていました。この時点でまだ相談までには至らなかったです。
保健師さんに相談を決意
その後、1ヶ月くらい吃音が出て2ヶ月くらい吃音なし。 このサイクルで3サイクルくらい続いた時に、

わーわー、わーたしね

あれ、今までと違う?
繰り返しでなくて、最初の言葉伸ばしていない??
一段階吃音が進んで、伸発(最初の音が引き延ばされること)が出始めました。当時は不安でいっぱいでした。ネット情報で吃音の段階を見ていたので、
“ひどくなってしまった…”
“どうしよう”
“なんとかなると放置していたからではないか”と自分を責めました。
保育園に通っていたので、担任の先生には状況を共有していましたが、園の先生も「吃音」という言葉すら全く知らない状況でした。園ではたまに出ているかな程度ですというお話でした。
当時の環境の変化が影響したのかもしれないとも思いました。
ちょうど真ん中の長男の出産間近の時期で色々な状況が重なり、不安、心配を感じたのではないか、、、。
当時、妊婦だった私はそこまでの余裕があるわけではなく、これからの出産、その後の生活の変化にドキドキして生活していました。ですが、娘からの吃音のサインにこれは自分たち親で解決できる問題ではない、娘の吃音と向き合わなければいけないと市の保健師さんに相談することを決意しました。
出産後は、保育園の先生に園での吃音の様子を報告書として書いてもらえるようお願いしました。そしてその報告書とともに言語相談に行きました。実際に相談できたのは、長男の出産後3ヶ月経過した頃。娘の吃音が出て、1年が経とうとしていました。
まとめ
今回、娘の吃音が出てからその後言語相談を受ける決意をするまでをお話しました。
吃音かもしれないと頭をよぎった時、それをそのまま素直に受け取ることはできませんでした。“どうして…”と疑いから始まって、向き合うまでも1年という時間がかかりました。
当時、吃音がでなくなって一喜一憂していた時に長男の妊娠が発覚。そこから自分の体調の変化と向き合いながらの、娘の吃音と向き合うには正直かなりのエネルギーが必要でした。
たくさん話してくれようとする娘を見て、“どうにかしてあげたい、、、”“どうしたらいいのか”と頭の中でずっと考えていました。でも周りには吃音の子どももおらず、相談するという気持ちにはなれませんでした。
吃音には波があります。吃音が出る期間が1ヶ月、吃音が出ない期間が1ヶ月といったサイクルで波を繰り返します。波があることを覚えておくだけで一喜一憂する気持ちが減るかもしれません。
また、余裕がある時でもいいので、吃音が出始めた時に、“何がきっかけだったか”を振り返るといいです。そーすると、安心して楽しく話せる環境づくりに注力できます。
その環境づくりをして、話し方ではなく話す内容に耳を傾け、伝わった喜び体験を増やしていきましょう。
現在、我が家では言語聴覚士の先生と話したり自分たちで勉強した中で、心構えは下記のようにしています。
①自分達を責めない
→吃音は親の育て方、しつけと関係はない
②大切なことは、治らなくても困らないように対応をしておくこと
→治る人も多いけれど、大人になっても吃音が残る人がいるのも事実
③伝わった自信や喜びを感じられ、楽しく話せる環境整備をする
→話し方でなく話している内容に注目
→ゆっくり、落ち着いてとかの声かけはしない
→スラスラ話せなくても良いという安心できる雰囲気
今後は、
・我が家は、吃音の事実をどう受け入れていったのか?
・言語相談→言語支援教室へ通うまでの流れ、
・保育園、小学校、学童への対応
などもお話していこうと思いますが、
次回は、保健師さんとの相談内容や面談の様子についてとそこからの吃音との生活についてお話します。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
今、娘は小学生ですが、波はあるものの吃音はまだあります。
親子で心地よい付き合い方を模索していますが、人に恵まれたこともあり、比較的うまく付き合っていると思います。
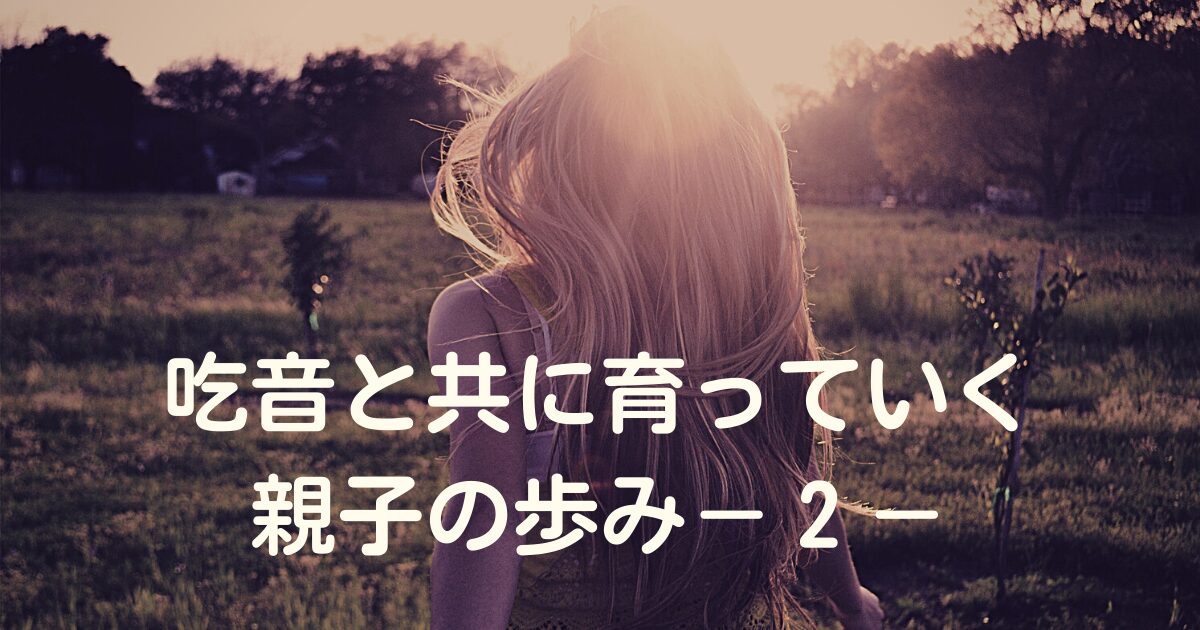





コメント