「吃音」(きつおん)という言葉をお存じでしょうか。
まだあまり馴染みがない方が多いかなと思います。私も、長女が吃音になるまでは言葉すら知りませんでした。
あまり馴染みがないので、公表することに緊張と不安がつきまといながら現在書いていますが、長女が吃音について夏休みの自由研究でみんなに話す!という言葉を聞き勇気をもらって書いています。
そもそも吃音とは、言葉がスラスラと出てこない言語発達のことです。
我が家の吃音との向き合い方や、親としてのマインド(心構え)、長女への接し方などをお伝えします。
本記事は下記の方におすすめです。
・吃音のお子さんがいらっしゃる方
・吃音について不安や悩みを打ち明けられず不安な方
・吃音とどう向き合っていけばいいのか迷っている方
吃音の度合いや本人がどこまで気にしているかなどでケースが違ってくると思いますので、
あくまでも我が家の長女の場合の情報発信になります。同じ悩みをもつ親、吃音に悩む子にとって少しでも気持ちよく、楽しく、おしゃべりして過ごすための参考になったら嬉しいです。
本記事は子供の「吃音」に悩むご両親や、ご本人や、身近に吃音の人がいて接し方に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
吃音とは
吃音とは、言葉をスラスラと話せずに、どもってしまう言語発達で、言語障害の1つです。
昔は、親のしつけ、育て方が悪いなどと言われている時代もありましたが、最近の研究では、吃音は親のせいではなく、もって生まれた体質によるところが大きいとわかってきています。
【吃音のタイプ】
吃音には、3つのタイプがあります。
①連発(最初の音でつかえて、同じ音を繰り返すことです)

お、お、お、お、お、おかあさん!
②伸発(最初の音が引き延ばされること)

おーーーーーーーーかあさん!
③難発(タイミングがとれずに言葉が出てこなかったり、最初の音だけが大きくなる)

…… ……. ….. おかあさん!
①→②→③へなるほど、本人の心理的負担は大きくなります。
調子が良い時は、吃音が出ていなかったり、①連発のみの場合もありますが、調子が悪い時は、③難発になり、手や足でタイミングをとる随伴症状もみられることがあります。
吃音は調子が良い・悪いで波があるのが特徴です。
【吃音の割合】
吃音は、4歳までに20人に1人が発症すると言われています。8割くらいは治る子もいますが、成人になっても吃音が残る人もいます。治る治らないに関わらず、子どもが吃音をマイナスなイメージと捉えることがないように対応をしていくことが大切です。
吃音を発症する前の様子
長女が吃音を発症したの3歳の時。発症する前触れとまではいかないですが、発症する前にいくつか心配な事がありました。
長女は恥ずかしがり屋で緊張しいの性格。知らない大人の方(保育園の先生も含めて)に話しかけられると、私の後ろに隠れてしまう子でした。そんな長女が保育園に通い始めたのが2歳の頃、、、最初は緊張から1ヶ月間先生の問いかけに口をききませんでした(苦笑)完全無視…先生も大変だったと思います。
少しずつ保育園生活に慣れてきていましたが、そんな頃に、少しの不安や緊張をある自傷行為でアピールするようになりました。それは、爪むしり…。保育園で指1本、2本と度々爪をむしって帰ってくるようになりました。
心配で園にも様子を見てもらいました。娘は初めての事、場所、人、物、全てにおいて不安を持ち、
それを言葉にできない代わりに爪をむしっていたようです。ひどくなると出血する程むしってしまうこともあり、なぜ、、、どうしたら、、、ととても不安でした。
なぜやってしまうのか?、いつやってしまうのか?と考えた時に、園での大きな行事(夏祭り、運動会 etc…)の前に、爪むしりがひどくなる事が分かりました。家では安心できるように寄り添い、爪をむしらないように声をかけたり、子ども用のマニキュアを試したりもしました。
吃音の発症前は、そんな日々を送っていました。
※恥ずかしがり屋、緊張しいの子や自傷行為をしてしまう子が吃音になるわけではないです。
吃音のはじまり
始まりの日は忘れもしません。園の発表会の前日、園の給食の話をしている時に、、、

は、は、は、は、は、はんぺん
今までスラスラとスムーズに話すことが多かったので、その一言がとても気になったのをよく覚えています。
この日から吃音は始まりました。
その日を堺に、頻繁に吃音がでるようになり、私は戸惑いました。
何も知識がなかったので、“どうしてそんな言い方をするんだろう”“何かあったのか”と不安で不安で調べ続けた記憶があります。今思えば、その日から“吃音”と分かるまでが辛く長い日々でした。
この後、吃音が始まってからどうなっていったかは、また次回お伝えしたいと思います。
現在の我が家の吃音との付き合い方
基本的に子どもとの会話の中で吃音の話を隠すことはありません。吃音に触れないように過ごしている方も多いと聞きますが、“隠す”“触れない”ことによってより“吃音は隠すもの”という認識になってしまうからです。吃音=隠さなければいけないものではありません。
我が家は吃音は長女の“話し方”であって良い悪いではないこと、そして吃音についての会話をよくしています。吃音は長女の一部です。長女=吃音だからと決めつけることもしていません。
ただ、吃音が辛いものにならないように、吃音を発症してから様々な方と話し合い、連携させていただきながら今日まできています。
吃音は言葉が出づらいので、話し方に注目がいってしまうことが多くあります。ですが、注目してほしいのは話し方ではなく話す内容。話したい内容を本人が伝えようとすることが大切になってきます。ですので、基本話が終わるまで待ちます。長くなって本人が苦しくなりすぎてしまう場合は途中で声をかける時もあります。
そして吃音が出ていると、その様子から心配になって「ゆっくり落ち着いて」と言いたくなります。
ですが、本人は焦って話しているわけでも、急いで話そうとしてスラスラ話せなくなっているわけでもありません。ただ話そうとしているだけなんです。なので、“落ち着いて”という声かけは逆に不安にさせてしまいますので、我が家では決して言いません。子どもの言いたいことを先取りして言いたくなる時もありますが、それもしないようにしています。
子どもが話すこと自体を嫌にならないように、話したい内容が親に、先生に、お友達に伝わって自信や喜びを感じられる環境が多いように、スラスラ話せないかもしれないけれど話すことが楽しいと思えるように安心できる環境をつくっていくことを心がけています。
子育てをしていると、きちんと子どもの話聞くことは簡単ではありません。
忙しなくすぎていく中でつい先取りしたくなりますが、そこは一呼吸置くようにしています。
あまり神経質になると親の方が参ってしまう時もありますので、話を聞けない時は素直に「ごめん。今忙しくて話を聞けないから後でお話してくれる?」と言って、ちゃんと後で時間を作って聞くようにしています。
まとめ
言語聴覚士の先生と話したり、自分たちで勉強した中で我が家の心構えは
・吃音を特別扱いせずにオープンに話し合っていくこと
・伝わる自信や喜びを感じられ、楽しく話せる環境を意識すること
我が家が、吃音の事実をどう受け入れていったのか?
次回以降、我が家が言語相談までたどり着いた経緯、そしてそこから言語支援教室へ通う日々や保育園、小学校、学童への対応について書こうと思います。
今、娘は小学生ですが吃音があります。親子で心地よい付き合い方を模索しています。
吃音と向き合いながら、自分でできることを日々模索しています。
“自分にできること”を見つめていきませんか。
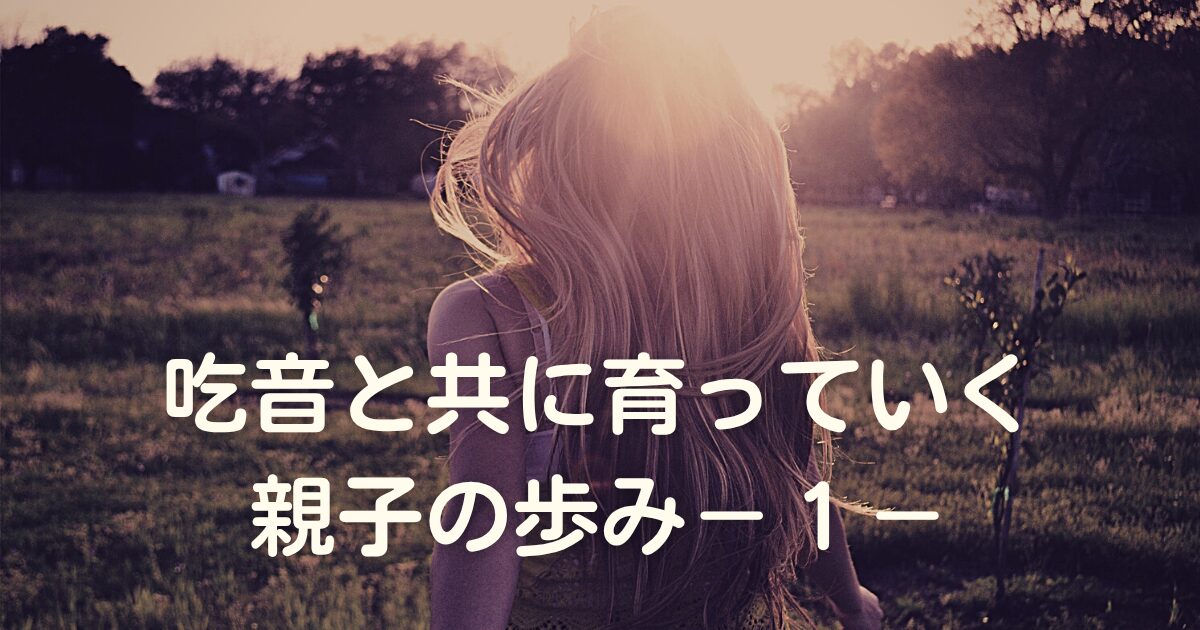





コメント