こちらのブログでは、娘の「吃音」についてお話ししています。
お話はこちら↓↓


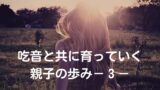
吃音とは、言葉がスラスラと出てこない言語発達のことです。
回数を分けながら、我が家の娘との吃音との向き合い方や、親としてどういうマインド(心構え)を持ち、接しているかなどを発信しています。
吃音の度合いや本人がどこまで気にしているかなどケースが違ってくると思いますので、あくまでも我が家の場合での情報発信になります。ご了承ください。
前回は“1回目の言語相談を受けてからも吃音がひどくなってしまった話”についてお話しました。今回は、2回目の相談を受けてそこから吃音のコミュニケーション教室に通うようになったお話をします。
2回目の言語相談の日まで
1回目の言語相談では良い方向に向かわなかった娘・・・。

・・・・・っわたしね
と吃音症状は“難発”という一番ひどい段階になっていました。
常に難発がでるわけではありませんでしたが、難発は言葉が詰まるので、顔をくしゃっとさせてとても苦しそうに話す姿に不安しかありませんでした。
“相談してアドバイスももらったし、良くなっていくだろう”
と思い込んでいた私は、どんどん焦りが出始めます。
“なんでこんなことに・・・”
“このままひどいままだったらどうしよう・・・”
とネット情報や本を参考に試せるものは試しました。
吃音の波に、一喜一憂しないように。。。
それでもどうしても難発を目にすることが多くなっていき、難発で言葉が出ないことで身体を揺らしたり叩いたりとタイミングを取って話すようになりました。
そして娘自身もそれを自覚し、話すことに躊躇したり、イライラする姿も見られるようになりました。
“このままでは娘が話さなくなってしまうかもしれない”
“たくさん話したいことがあって話そうとしているのにそれが出来ないからもどかしい”
娘を見てそう感じた私はもう一度言語相談をすることを決めました。
相談する先は、そこしか考えられませんでした。周りに相談しても“分からない”“知らない”という言葉が飛び交ってきそうで周りに相談する勇気がありませんでした。
そんな思いで2回目の相談日を迎えます。
コミュニケーション教室を勧められる
言語相談は、前回と同じ言語聴覚士の方が担当してくださいました。
吃音を学んでいて、吃音の研究や吃音教室を開いている先生と繋がりがある方です。
言語聴覚士の方に、1回目から今回までに起こっていた娘の様子を話しました。

吃音が難発になっている時が増えています。
身体でタイミングを取って話す時があります。
このままで良くなっていくとは思えなくて・・・。
1回目に相談したときよりもひどくなっているということを話しました。
言語聴覚士の方の前ではあまり吃音がでない娘ですが、それでも優しく様子を観察してくださり、こう声をかけてくれました。
『いつもそばで見ているお母さんがそう思うタイミングはとても大事だと思います。吃音を研究している先生が“コミュニケーション教室”を運営しています。そこでもう一度、見てもらいませんか?』
そう声をかけられたことで一筋の光が見えたと同時に現実も突きつけられます。
『そのコミュニケーション教室に通うには市に書類を提出して受給者証というものを発行してもらう必要があります』
この言葉にまた心がグッとなりました。
受給者証とは、障がい児通所サービスを利用する際(未就学児対象の児童発達支援など)に交付されるものです。(市によって異なるかもしれません)
日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障がい児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行うというものでした。
※現在は北海道に移住し、色々な事情で受給者証はもっていません
この“障がい児”という言葉がまた私の中で引っかかってしまいます。向き合う覚悟ができてるように見えて、いざ言われるとまた動揺してしまう自分がいました。全然覚悟ができていなかったわけです。
“言語発達障がいという事実”と“通所する”ということに、何だか気持ちが追いつきませんでした。
ですが、娘の苦しんでいる姿をなんとかしたい、もっと楽しく、楽に話せるようなったら、そんな思いが後押しし、まだ気持ちは整理できていませんでしたが、通所できるように手続きをしました。
コミュニケーション教室初日
無事に、受給者証を発行できたので、コミュニケーション教室に予約をして伺いました。
そこは、一軒家を借りて運営しており、アットホームな感じがありました。
初めての場所に緊張感もあった娘ですが、暖かく迎えてれてくださった先生方。
ゲームなど楽しみながら話をするといった流れでした。
今までの娘の経緯は、言語相談で担当してくださった方から連絡を受けていたそうで、スムーズに吃音の話をすることができました。
その時コミュニケーション教室で大事にしていることを話してくれました。
・話すことが楽しくそして楽に話せること
・お友達から吃音の話し方について聞かれた時の応え方
・からかいが起きないようにするためにできること
・親の吃音に対しての向き合い方
吃音とはという話から、色々な場面での対処法など話してくれました。
その中でも一番大切なことは“親である私達の向き合い方である”ということを言われました。
“いくら家の外で頑張っても、安心できる場所(家・家族)がなければ続かない”
親である私達が吃音と向き合っていくこと。全てを今すぐ受け入れられなくてもいい、受け入れられないことがあった時はすぐに教えて下さいと言ってくださいました。
そして、
娘=吃音ではなく、
娘の話し方=吃音の時がある
であること。吃音はがダメなことでも、恥ずかしいことでもないこと。
それを親である私達が理解するともに、言葉にして、少しずつでもオープンで話していくようにしていくこと。
様々な刺激あるお話をしてくださいました。
コミュニケーション教室に月2回通い始める
その日から、教室通いが始まりました。月2回で1回1時間程。
その時の状況に応じて回数を減らしたり増やしたりします。
最初の数回は親も同伴でしたが、その途中からコロナが流行・・・
途中からは娘一人で教室に通う日々が続きました。
始めは緊張からあまり話していない様子だった娘も回数を重ねるごとに慣れ、たくさん話をするようになったそうです。その中で、吃音がでている様子も見てもらえ、“家での状況を共有できた”と安心できたことを覚えています。
半年程経って5歳を迎えた頃、1度言語の知能検査を受けてみませんかというお話を受けました。
言語の発達についてのどのくらいなのかを把握しておきたいとのことでした。
しっかりと見てもらった方が娘のためにも、そして自分の気持ちも引き締まるかなと思ったので、検査を受けることにしました。
検査結果は言語の“理解力”に関して実年齢よりも遅れているという結果でした。
理解力が低いことで、言われたことが理解できずに混乱し、そこから何を伝えればいいのかという不安に繋がる可能性もあるとのことでした。
その不安を取り除くように支援していくことで、より自信をもって話せるようになっていくとのことでした。
実際に娘の言語力に“幼いな”と感じる部分があったので、そこがはっきりわかったことで、もっと娘を知ることできたと安心したと共に、関わり方も向き合い方も、もう少し娘に寄り添っていけるなと思いました。
知能検査をすることで、吃音が解消するわけではありません。色々なアプローチの一つだと考えていただけるといいかと思います。
私は、娘が教室に通うということ自体を時間をかけて受け止めていきましたし、知能検査の結果を先生から伝えられた時は、泣きました。いつも見ている我が子の事を知る道標になったと安心の方が強かったのを覚えています。
まとめ
今回は、2回目の相談を受けてコミュニケーション教室に通うようになったところまでお話しました。
2回目の言語相談をした時、頭の片隅では、“言語発達障がい”という言葉がよぎり、子どもは大変な思いをしながら生きていくのかもしれない、と不安に襲われました。
何もできないなと、自分が無力でとても落ち込みました。ただ、相談することしかできないと…。
“障がい”という言葉を言われた時には、“自分の子どもに障がい・・・?”となんともいえない思いになりました。“どうして”“なぜ”と思い、胸が苦しくなりました。
この時に感じたことは“何かの言葉に縛られてしまう怖さ”です。
今まで
“障がい”とは“目に見えるもの”
と私自身思い込んでいたのかもしれません。
娘は話さなければ障がいだとは分かりませんし、波があるので話していても気付かないこともあります。
“障がい”という言葉の重さをそこで初めて感じました。そして障がいというものの見方もそこから変わりました。
自分の子どもに障がいがあると認めたくない思いももちろんありました。それは未来への不安があったから。。。認めること、向き合うことは決して簡単なことではありませんし、私自身、今もその“障がい”という言葉と向き合っています。
辛い思いを抱えている時、それを言えない雰囲気、環境を恨んだこともありました。
小さな勇気を出して言えればそれは新たなスタートになりますが、それも簡単なことではないです。
でも私がこうしてブログで綴っているのは、“自分以外にも向き合ってくれる人は必ずいる”ということを伝えたいからです。
必ず、受け止めてくれる人はいます。そして知ってもそばにいてくれる人も。。
次回は、コミュケーション教室に通っている中で起きた、保育園での出来事についてお話します。保育園の先生方にもお伝えをしてる中で、お友達から“吃音への疑問”をぶつけられた娘。その時の様子と対応をお話します。
現在、我が家では言語聴覚士の先生と話したり自分たちで勉強した中で、心構えを下記のようにしています。
①自分達を責めない
→吃音は親の育て方、しつけと関係はない
②大切なことは、治らなくても困らないように対応をしておくこと
→治る人も多いけれど、大人になっても吃音が残る人がいるのも事実
③伝わった自信や喜びを感じられ、楽しく話せる環境整備をする
→話し方でなく話している内容に注目
→ゆっくり、落ち着いてとかの声かけはしない
→スラスラ話せなくても良いという安心できる雰囲気
今後も引き続き、
・我が家は、吃音の事実をどう受け入れていったのか?
・保育園、小学校、学童への対応
などお話していきます。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
今、娘は小学生ですが、波はあるものの吃音はまだあります。
親子で心地よい付き合い方を模索していますが、人に恵まれたこともあり、比較的うまく付き合っていると思います。
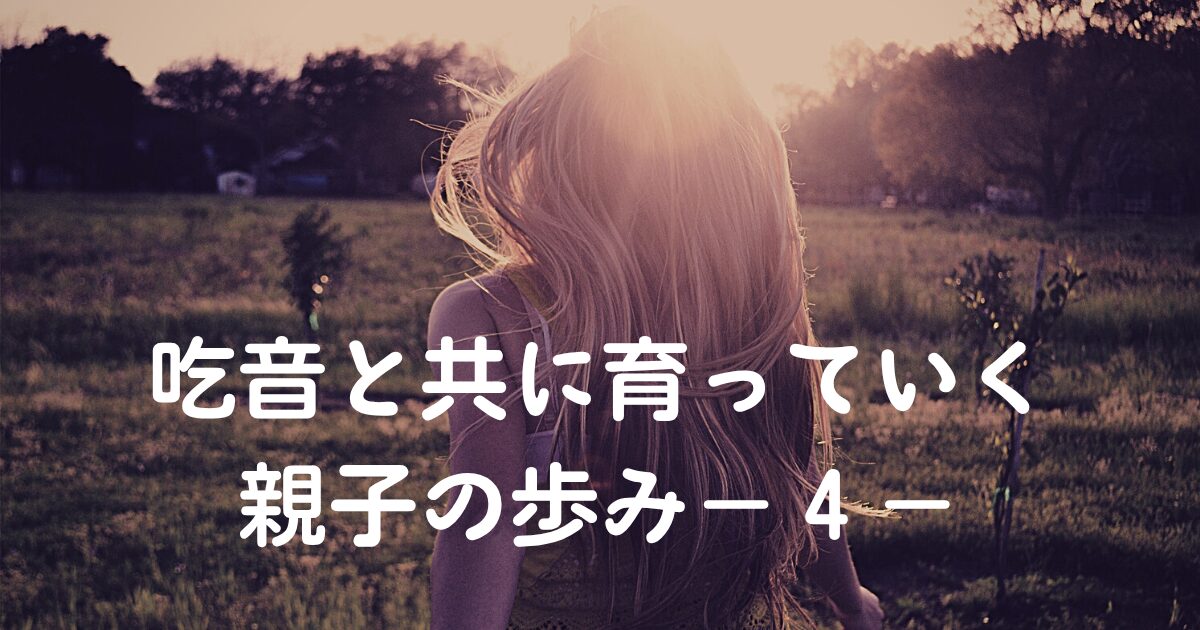





本記事は、子どもの吃音で悩んでいる方、吃音に悩み苦しんでいる方が、
少しでも前を向いて過ごせるための参考になったらうれしいです。